【Case25:三菱電機の場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜
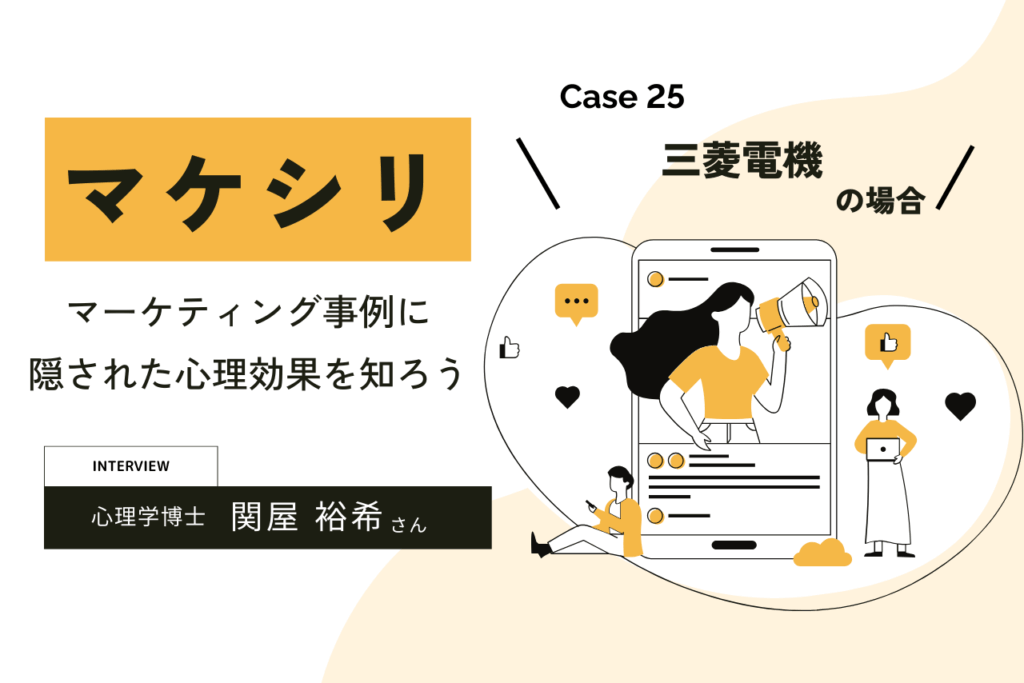
マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!
弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya
1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身
せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。
ホームページ:https://www.sekiyayuki.com
2025年8月4日からスタートした、三菱電機による企画「もしも機械が休んだら〜機械の休日〜」についてご紹介します。
この取り組みは、日本機械学会が制定する「機械の日(8月7日)」と「機械週間」にあわせて展開されたプロジェクトで、私たちの暮らしや社会を支える機械がもし一斉に休んだらどうなるのか?という想像をもとに、機械の価値と存在意義を問い直す内容となっています。

引用:https://predge.jp/324531/
特設サイトでは、三菱電機の自動化技術を支える機械たちを紹介するWebムービーや、機械のキャラクター紹介など、子どもから大人まで楽しめるコンテンツを多数用意していました。さらに、8月22日から24日の3日間限定で、イラストレーター・田中光さんによる描き下ろし作品を展示したリアルイベントも原宿で開催されました。
人と機械の適切な関係を見つめ直すことを目的とした本企画は、機械が担う役割への理解を深めると同時に、若者の「ものづくり離れ」や少子高齢化による人手不足といった社会課題への気づきにもつながる、意義深いブランディングプロジェクトとして注目されています。
機械に休みを与えることで、人の働き方を考えさせる
──今回の企画、テーマが「機械の休日」ってユニークですよね。
関屋:そうですね。機械って、基本的に「止まらないもの」というイメージがありますよね。でも、そこに休みという人間的な概念を持ち込むことで、見る側は一気に感情移入しやすくなる。
冷たく無機質な存在だったはずの機械が、ちょっと疲れて休んでいるとしたら…? そう考えると「普段当たり前に使っている技術やインフラ」に対して、自然と感謝や関心が湧いてくるんです。
「誠実そう」「裏表なさそう」──登場人物から伝わる信頼感
──登場人物も若い人ばかりで、好印象でした。
関屋:そうなんですよ。実際に動画に登場している若手社員の表情や語り方が、とても自然で、誠実さを感じさせました。視聴者は、自分と年齢が近い登場人物に自分を重ねやすいんです。
映像では、若手社員が機械の仕事に実際に挑む様子が淡々と映し出されています。過度な演出や強いメッセージは使わず、表情や動き、シンプルなナレーションなどで構成されていて、「堅実そう」「ワークライフバランスが良さそう」といった印象を自然と受け取りやすくなっています。
また、登場する人たちが自分と年齢の近い世代だと、視聴者も「この会社、自分にも合うかも」と感じやすいんです。こうした印象の良さが、企業全体へのイメージにもつながっていくと思います。
「暮らしの中にもある会社」という親近感を引き出す
──三菱電機って、生活でもよく目にする会社ですよね。
関屋:そうですね。冷蔵庫やエアコン、テレビなど、家電の印象が強い方も多いと思いますし、実際に私たちの暮らしの中で当たり前に存在している会社です。
今回の企画は、そんな「いつも身近にある機械」がもし休んだらどうなるかという視点で展開されていますよね。この問いかけがとても良くて、ただ製品を紹介するよりもずっと自然に「役に立っていること」や「なくてはならない存在」であることに気づかせてくれるんです。
そうやって、技術とか産業という言葉だけじゃ伝わらない価値を、生活者の目線に置き換えて伝えている。難しいことをシンプルに見せるのが、とても上手なプロモーションだと思います。
リアル志向の就活生に刺さる、働く現実の描き方
──採用目的も見据えたプロジェクトだったそうですが、若者への刺さり方はどうでしょうか?
関屋:かなり良かったと思います。最近の就活生は理想よりも現実を見る傾向が強い。「この企業で働いたらどうなるのか」「年収は?」「ワークライフバランスは?」みたいな。そうしたリアリズムを受け止めたうえで、今回のような落ち着いたトーンの企画は、とても効果的です。
派手な演出ではなく、誠実さや実直さがにじみ出ている。これは若者にとって安心感につながりますし、「こういう会社で働くのもアリだな」と思わせる説得力があります。
まとめ
機械が止まったら社会が止まる。けれど、普段は誰もその当たり前を意識していない。
そんな視点からスタートした今回のプロジェクトは、「ものづくりの価値」や「支える仕事の魅力」を生活者にも、就活生にも伝えることに成功していました。
見た人が「なんかいいな」と感じるあの空気感には、感情移入、共感、信頼といった心理効果がきちんと働いていたからこそ。三菱電機のような老舗メーカーが、若年層向けにここまで振り切ったプロモーションを行ったこと自体にも、大きな意味があると感じます。
