【Case22:オーラツーの場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜
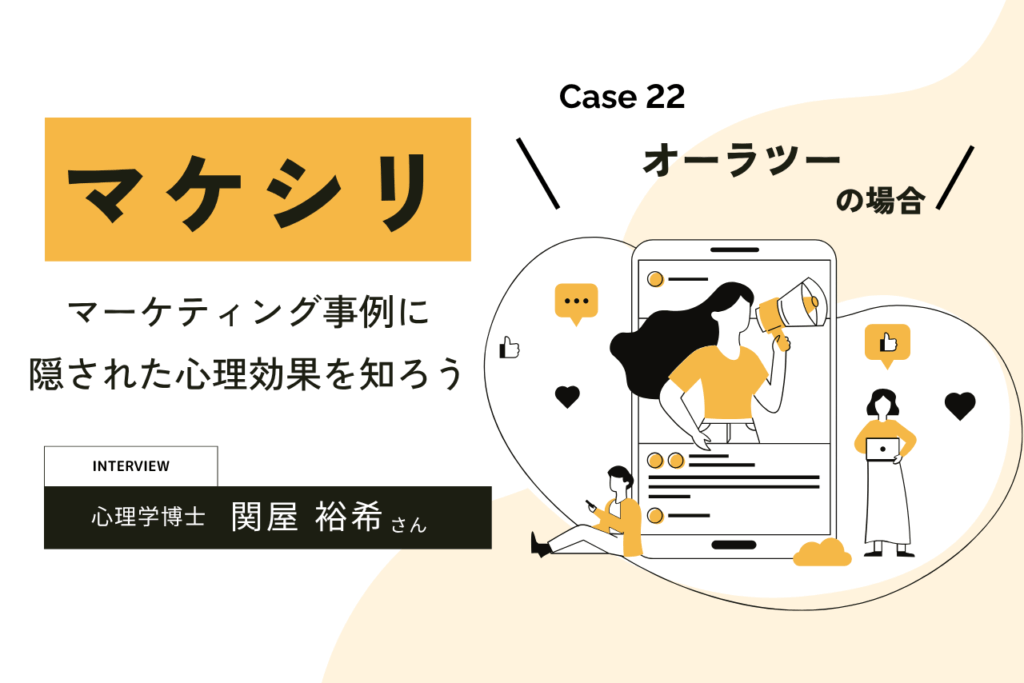
マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!
弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya
1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身
せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。
ホームページ:https://www.sekiyayuki.com
2025年6月9日からスタートした、サンスターのオーラルケアブランド「Ora²(オーラツー)」による新プロジェクト「#昼休みに自由を」についてご紹介します。
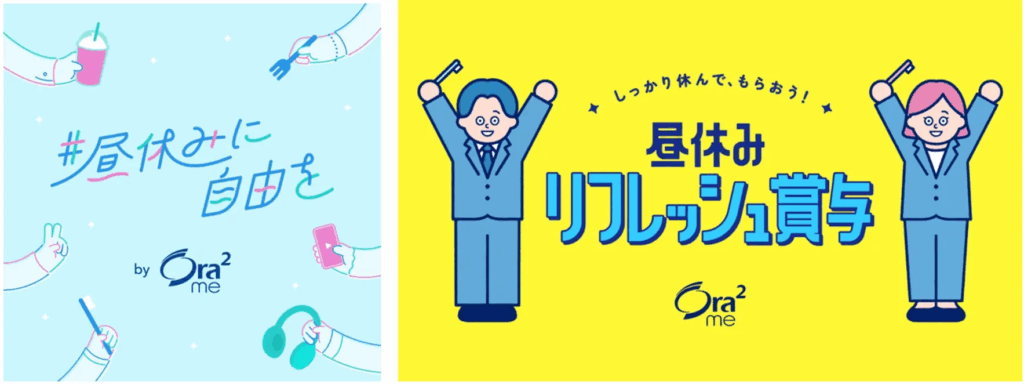
この取り組みでは、昼休みをただの休憩時間ではなく「自分らしくリフレッシュする時間」と捉え直し、歯磨きをアイテムとして活用。20~30代の社会人を対象にした調査では、約86%が午後からのモチベーション維持に昼休みのリフレッシュが重要と回答する一方で、約61%が実際には昼休みをしっかり休めておらず、約75%が十分リフレッシュできていない現状が明らかになりました。
そこで同ブランドは、昼休みの“自由な過ごし方”をSNSに投稿すると賞与がもらえるユニークなキャンペーン「昼休みリフレッシュ賞与」を実施。投稿者には抽選で1,000円分の「えらべるPay®」をプレゼントし、商品を使った「昼みがき」投稿では賞与額アップの仕組みに設定。さらに参加者が10,000件を突破すると賞与が増額される仕掛けも用意されています。
このプロジェクトは「昼休みのリフレッシュが仕事のパフォーマンスにつながる」というメッセージを、楽しみながら“疑似体験”できる仕掛けが詰まった、新感覚のプロモーションとして注目されています。
「昼休みって、ちゃんと休めてますか?」
──関屋さん、この施策のどこがポイントだと感じましたか?
関屋:まず大前提として、人の集中力や判断力、いわゆる「認知資源」って、使えば使うほど消耗していくんです。これを回復するには、しっかりとした休憩が必要。
だから「昼休みにちゃんと休もう」という提案自体が、科学的にもすごく理にかなっているんですよ。
認知資源
認知資源とは、人が思考、判断、注意を向ける際に使う脳のエネルギーや能力のことです。これは有限な資源であり、使えば消耗し、不足すると集中力や判断力の低下につながります。
歯磨き×リフレッシュの心理設計
──今回は“昼磨き”という行動にも注目が集まっているようですね。
関屋:そうですね。「食後に歯を磨きましょう」と言われても、忙しい社会人にとってはなかなかハードルが高い。
でもこの施策は、「昼磨き=気分転換になる」「健康にもいい」「しかも賞与がもらえるかも」というように、複数のモチベーションを同時に刺激しているのが非常に上手いですね。
「脅し」ではなく「ご褒美」で行動を促す
──歯磨きを促す広告って、つい「虫歯になりますよ」というような注意喚起が多い印象があります。
関屋:それがこのキャンペーンの面白いところです。従来の“脅し型”メッセージではなく、「やったら良いことあるよ!」というインセンティブ型にシフトしているんです。
「#昼みがき」を投稿すれば1,000円分の賞与がもらえる。しかも参加者数が増えれば、賞与額も増えるという“ゲーム性”まで加えられているのがユニークです。これにより、ただの個人の健康習慣にとどまらず、チーム全体や職場全体で取り組みたくなる仕組みになっているんですよ。
リフレッシュとパフォーマンスの関係
──「昼休みの質が午後のパフォーマンスに影響する」という話は実感ありますよね。
関屋:そうですね。人間の脳はずっと集中し続けられるわけではありません。昼休みを使って休息をとったり、気分を切り替えることで、午後の判断ミスが減ったり、作業のスピードが戻ったりします。
今回は、「歯磨き」という簡単なアクションをリフレッシュのきっかけとして提案しています。
まとめ:健康習慣は“楽しさ”と“共感”で作れる
オーラツーの「#昼休みに自由を」は、昼休みのあり方を見直すと同時に、“歯磨き”という健康行動のハードルを下げる優れたプロモーションでした。
健康習慣は「やらなきゃダメ」よりも、「やると楽しい・得をする」設計の方が、長続きしやすい。今回の事例は、マーケティングにおいても、心理学的な視点からも、非常に学びの多い内容でした。
──関屋さん、本日もありがとうございました!
