【自己肯定感の教科書】「自分を信じる力」はどう育てる?
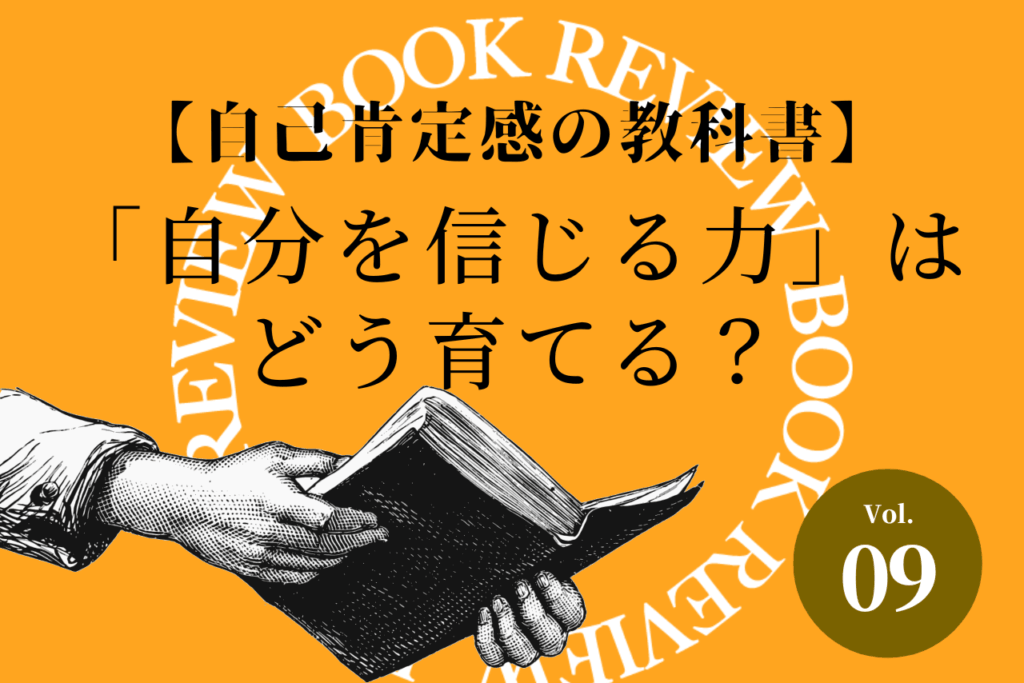
「心理学」「脳科学」関連の書籍を読んで、blogle編集部が感じたことをお伝えしていくコーナーです。
今回は「どうすれば“自分を信じる力”を育てられるのか?」というテーマでお話したいと思います。
このテーマは【自己肯定感の教科書 ― 「自分を認めて幸せになる6つのステップ」著者:中島輝】に書かれている内容からインスピレーションを受けました。

今回お伝えしたい結論を先に言ってしまうと
「自己肯定感とは、“できる自分”を信じることではなく、“どんな自分でも大丈夫”と思える力のこと」「その感覚を取り戻すことが、幸せや前向きな行動の土台になる」
ということです。
「自分に自信がない」「他人と比べて落ち込んでしまう」―
そう感じたことがある人は多いのではないでしょうか。
今回ご紹介する『自己肯定感の教科書』は、
そんな“自分を信じる力”を取り戻すためのヒントが詰まった一冊です。
心理カウンセラー・中島輝さんの実体験をもとに、自己肯定感を回復するための具体的なステップが、やさしく語られています。
なぜ、私たちは自分を否定してしまうのか?
本書によると、人が自己肯定感を失ってしまう理由の多くは、
「過去の経験による思い込み」にあります。
たとえば、子どもの頃に「失敗してはいけない」「もっと頑張れ」と言われ続けた人は、
“できない自分”を責めるクセが身についてしまいます。
また、SNSなどで他人の成功を日々目にする現代では、
無意識のうちに「誰かと比べるのが当たり前」になっています。
でも、比べているうちは、永遠に満たされません。
なぜなら「上には上がいる」から。
中島さんはこう語ります。
「自己肯定感は、他人と比べることで生まれるものではなく、“ありのままの自分”を認めることで育つ」
自分を責めてしまうのは「弱さ」ではなく「そう思い込んできた癖」なのです。
自己肯定感を高める3つの習慣
中島さんは、自己肯定感を高めるために「特別な努力」はいらないと言います。
むしろ、日常の小さな行動を意識するだけで、心は少しずつ変わっていくのだと。
ここでは、本書で紹介されている考え方の中から、特に印象に残った3つを紹介します。
1. 小さな成功を認める
「こんなこと当たり前」と思っていることほど、実は大切です。
早起きできた、挨拶できた、ちゃんとご飯を食べた―。
そうした“できたこと”に気づき、自分を肯定する言葉をかける習慣を持つことが、心の回復力を育てます。
2. 感情を否定しない
落ち込む、怒る、焦る。
そんな感情を「ダメだ」と否定するのではなく、
「今、私は悲しいんだな」とそのまま認めてあげる。
それだけで、心は少し軽くなります。
感情を受け入れることが、自分との信頼関係を築く第一歩になるのです。
3. 他人と比べない
誰かと比べて安心したり、落ち込んだり―私たちはつい“他人の物差し”で自分を測ってしまいます。でも、比べる対象が変われば、評価も簡単に変わるもの。
大切なのは、「昨日の自分」と比べることです。
少しでも前に進んでいれば、それだけで十分。
本書は、そんな“等身大の成長”を見つける視点を教えてくれます。
「できない自分」も受け入れる勇気
自己肯定感を高めようとすると、
「もっと頑張らなきゃ」「変わらなきゃ」と自分を追い込みがちです。
でも、それでは本末転倒です。
中島さんは言います。
「できない自分を受け入れることこそ、自己肯定感を育てる一番の近道です」
失敗してもいい。
落ち込んでもいい。
人は誰でも、完璧ではありません。
自分を否定せず、「それでも大丈夫」と思える瞬間こそ、
本当の意味での“自分を信じる力”なのです。
自分を責める前に、「よくやってる」と言ってみよう
私たちは、誰よりも自分に厳しく、
つい「まだ足りない」「もっとやらなきゃ」と自分を追い込んでしまいます。
でも、本書を読んで感じたのは、
「がんばっている自分を認めることは、甘えではない」ということです。
むしろそれは、心の健康を保つ“メンテナンス”のようなもの。
疲れたときこそ「今日もよくやってる」と声をかけてあげてください。
“自分を信じる力”は、誰の中にもある
自己肯定感は、もともと誰もが持っている力です。
一度失われても、思い出すようにして少しずつ取り戻すことができます。
『自己肯定感の教科書』は、
「変わらなきゃ」と焦る心をやさしく包みながら、
“自分を信じる”という、いちばん大切な感覚を思い出させてくれる一冊です。
習慣も紹介していきたいと思います。乞うご期待ください。
