【Case26:印象に残る順番の魔法】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜
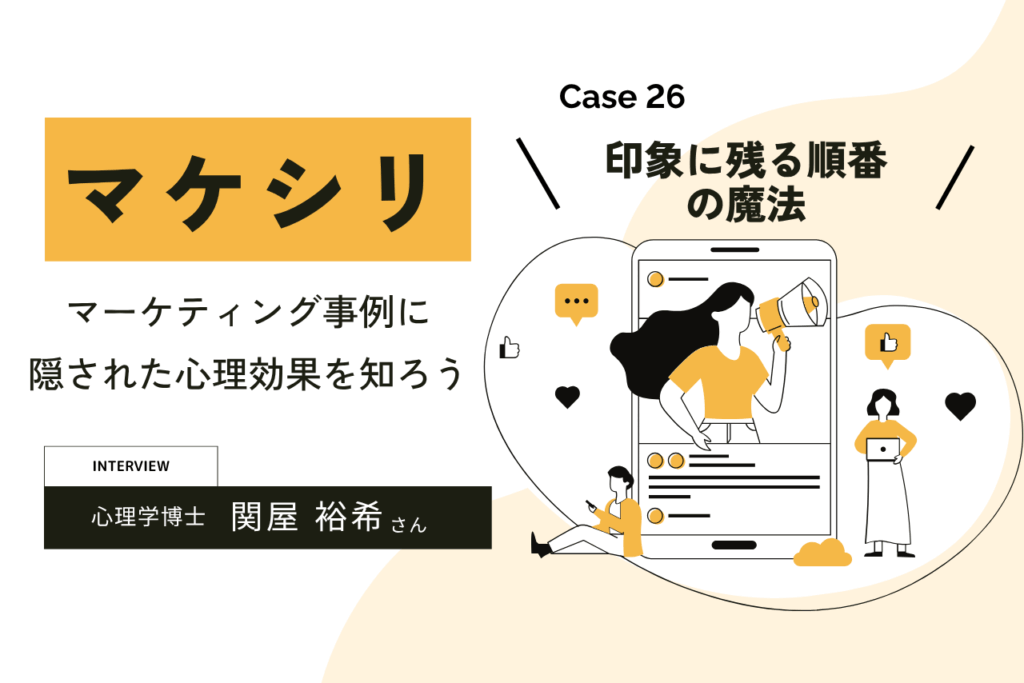
マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!
弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya
1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身
せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。
ホームページ:https://www.sekiyayuki.com
私たちは何かを判断するとき、意外にも「最初」と「最後」の印象に大きく影響されがちです。最初に得た情報が強く記憶に残る「初頭効果」と、最後に得た情報の印象が後を引く「新近効果」。
この2つは、広告やプレゼンはもちろん、レストランのコース料理や面接、商品の陳列など、あらゆるシーンで活用されています。

最初と最後は、なぜそんなに大事なのか?
──関屋さん、今日は「順番」についてのテーマですね。
関屋:はい。人って、意外と“真ん中”より「最初」と「最後」の印象で物事を判断しがちなんです。これは心理学で「初頭効果」と「新近効果」と呼ばれるものですね。
初頭効果は、最初に出会った情報の印象が強く残る現象。新近効果は逆に、最後の情報が記憶に残りやすいというものです。この2つは、商品プレゼン、面接、コース料理…あらゆる場面で活用されてるんですよ。
ビュッフェにも仕掛けられている“印象の順番”
──具体的にはどんな例が思い浮かびますか?
関屋:最近行った、グランドハイアットの中華ビュッフェがまさにそうでした。最初に出てくるのが、季節感のある一皿。ナス一切れとか、すごく小さいけどビジュアルが美しい。しかもコース仕立てで、その最初の一品がすごく丁寧なんですよね。
一緒に行った方が妊娠中で、あまり量は食べられない状態だったんですが、それでも「全部食べたくなる!」と言っていたくらい、小皿の見せ方や順番の設計が上手かった。見た目やサイズ感で期待値が自然と上がるような構成になっていて「これ美味しそう」「これも写真撮りたい」と思わされる流れができていたんです。
最後の印象で“全体の評価”が変わる
関屋:そして最後には、シンプルだけどしっかりと整ったデザートが出てくる。派手すぎず、でもちゃんと“締まる”印象なんですよ。こういう構成の丁寧さがあると、「また来たいな」って思いやすい。
逆に、どんなに素晴らしい映画でも最後の展開が微妙だったりすると、「あれ、そんなに良くなかったかも…」って感じたりしますよね。これはまさに、新近効果の影響です。最後の印象が、全体の記憶を上書きするんです。
ミャクミャクもその一例?“クセ強”でも印象に残る初頭効果
──ちなみに「万博のミャクミャクも最初のクセが強かった」って話も出てましたよね。
関屋:そう。最初に「え、なにこれ?」と思っても、そこから少しずつ慣れていくと「まあこういうものか」って受け入れやすくなる。これは心理的な“順応”の話にもつながります。
ただ最初がクセ強い場合でも、“次にくる情報がうまくフォローされてる”と、結果的にいい印象で終わることもあります。大事なのは、最初に目を引いて、最後で納得させること。やっぱり基本は「最初と最後」なんです。
まとめ:順番を制する者は、印象を制す
人の印象は、決して“全体の平均”では決まりません。むしろ最初の5秒、最後の5秒が強く心に残る。ビュッフェ、プレゼン、広告、イベント…順番の設計には、いつだって心理の仕掛けが潜んでいます。
何をどこに置くか。どんな一言から始めるか。どう締めるか。順番は、私たちが思っている以上に“記憶”や“好意”を左右する強力な要素です。
──関屋さん、本日もありがとうございました!
