【Case23:ファインディの場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜
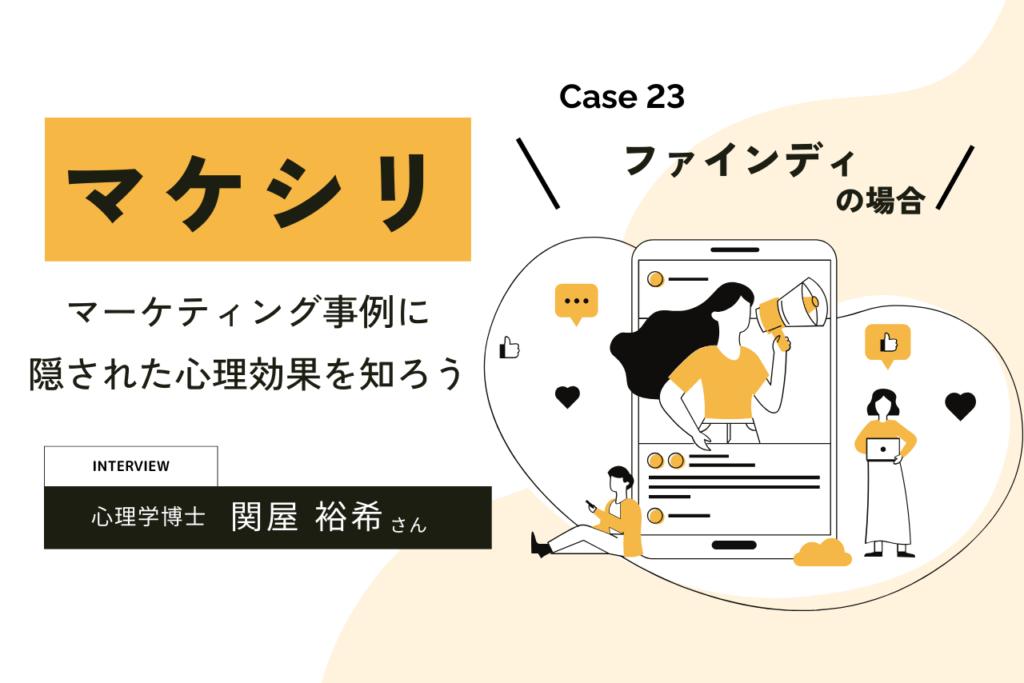
マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!
弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya
1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身
せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。
ホームページ:https://www.sekiyayuki.com
2025年7月7日、ファインディ株式会社は、新たなTV CM「つくる人が、世界を面白くする。」を放映開始しました。
このCMでは、人気アニメ『ドラゴンボールZ』から、発明家のブルマを起用し、彼女が開発した「ドラゴンレーダー」を象徴的なビジュアルとして提示。
ブルマを“日本が誇る天才エンジニア”として描くことで、エンジニアたちへの共感と応援メッセージを発信しています。
CMの放映と同時に、渋谷・秋葉原など都市部でブルマのキービジュアルを使った屋外広告(OOH)が展開され、世界中のエンジニアやファンに向けた訴求も視野に入れたデザインとなっています。
スローガン「つくる人が、未来を切り拓く」というコンセプトを通じ、現代の技術革新を担うエンジニアたちの働き方や社会的意義に焦点を当てたブランディング展開です。
ながら見では伝わらない
──ファインディのCMは、情報が極端に少なく、ブルマ(ドラゴンボール)の登場以外には、ほとんど何のサービスか分からない構成でしたね。
関屋:はい。こういった広告は、視聴者の「ながら見」を逆手に取った設計とも言えます。情報を詰め込んでも見流されてしまう時代に、あえて“何の広告か分からない”という違和感を生むことで、注意を引き、記憶に残す狙いがあると思います。
「作ろうぜ」の一言が刺さる
──CMの最後に出てくる「作ろうぜ」という一言が印象的でした。
関屋:あの言葉は、シンプルですが象徴的です。直接的な商品訴求ではなく、「ものづくりの楽しさ」「エンジニアの価値観」といった世界観を言葉ひとつで伝えている。これは“パーパスブランディング”と呼ばれるアプローチで、企業の価値観に共感してもらうことが目的です。強く売り込まれるよりも、自然な共感が生まれやすくなります。
パーパスブランディング
パーパスブランディングは、企業が社会の中でどのような役割を果たし、何のために存在しているのかを明確にし、それを外部に発信することで、顧客や従業員、投資家など、様々な人からの共感や支持を得ることを目指す戦略です。
あえて情報を欠落させることで、視聴者が「自分から調べたくなる」
──業種、サービス内容さえもほぼ明示されないCMでした。
関屋:そこにも心理的な仕掛けがあります。「認知的不協和」と言われる現象ですね。自分の中で“この広告、なんだったんだろう?”というズレが生まれると、人はそれを解消しようとして情報を自分で調べる。このCMは、その“知りたくなる感覚”をうまく活用していると感じました。
認知的不協和
認知的不協和とは、人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態のことです。この状態は、不安や不快感を引き起こし、人はそれを解消するために、自身の認知や行動を変化させることがあります。
広告疲れの時代だからこそ、押し付けない広告が刺さる
──今の時代、広告に対する拒否感も強まっていますよね。
関屋:まさにそうです。スマホ時代の今、情報過多で広告疲れしている人が多い。そんな中で「うちの製品を買ってください」と直接伝える広告よりも、受け手が“なんか気になるんだろう?と自ら関わりたくなるような設計のほうが、受け入れられやすいんです。
ファインディのCMは、そういった受け手主導の「能動的な関与」を引き出す工夫がされています。
まとめ:見せすぎない広告が、“知りたい”を生む
ファインディのCMに代表されるように、現代の広告は「伝えすぎない」「押し付けない」ことがむしろ効果的になってきています。
情報の空白にこそ、人の興味は引き寄せられる。心理的トリガーを的確に捉えた広告の形が、これからますます主流になるかもしれません。
──関屋さん、本日もありがとうございました!
